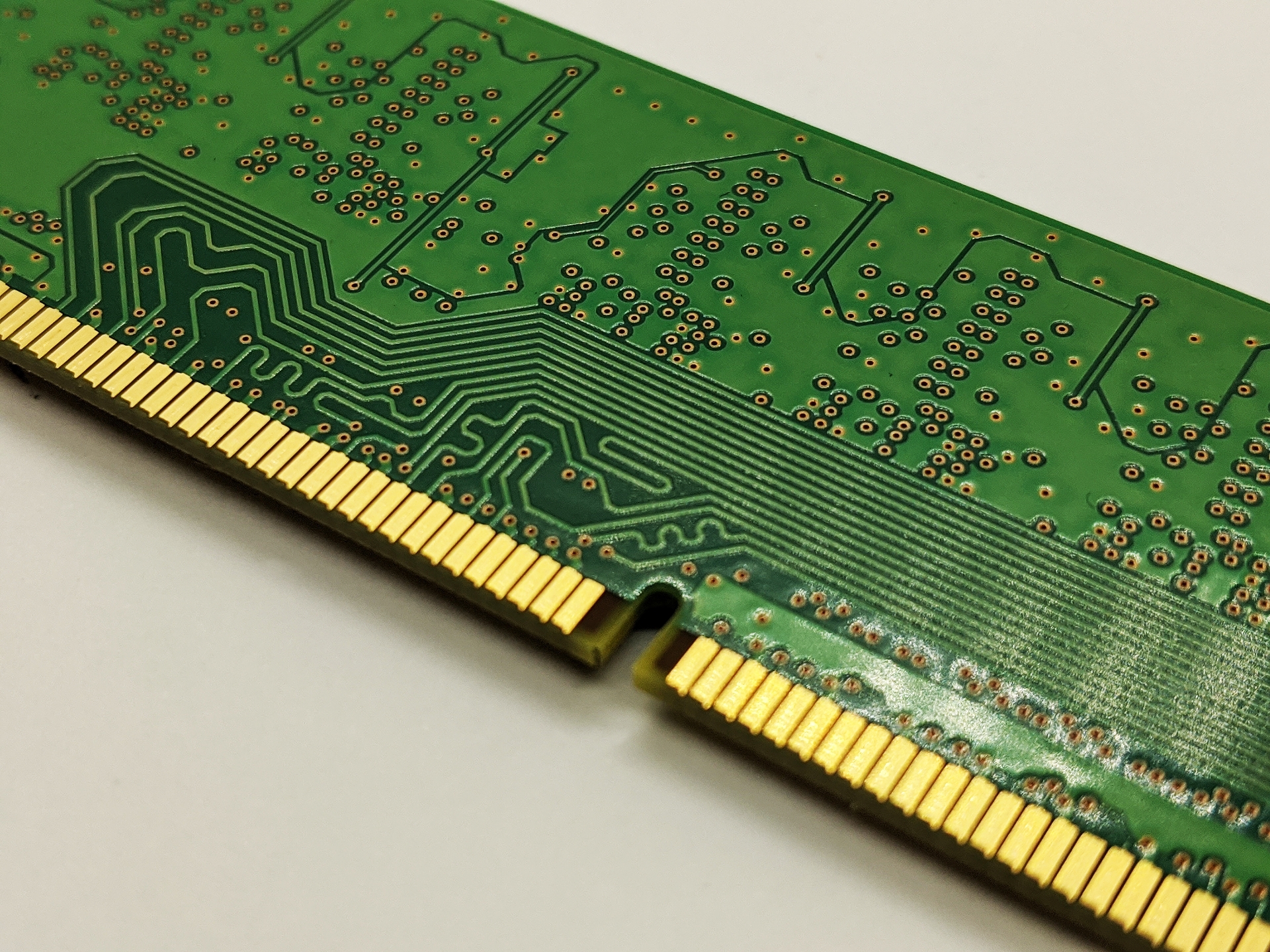「Intelligence(知能, 知性)」とはどんなものでしょう。
人間の知的能力を純粋に測るという概念に慣らされた近代以降の私たちは、「知能」が単独で純粋な能力値だと考えがちです。
しかし、知能テストは様々な試行錯誤を経て今の形になっています。
シリーズ初回として、まずは知能テストの成立までの歴史を概観してみましょう。

「知能」の小史
古典的な直感は、「知能」を「あるかないか」でニ分したくなりがち。
Homer(紀元前8世紀?)は「知能は一部の人に与えられた才能である」と考えました。
Shakespeare(1564-1616)は「ある問題を解ける人と解けない人がいる」ことを指摘しました。
「16世紀まで人類の(というか西洋の)知能観はほぼ進歩していなかった」と言えましょう。
16世紀、Juan Huarte de San Juan(1529-1588)は問題解決の2つの方法を提起しました
1.想像を駆使して解決策を生み出す
2.記憶にある解決法を当てはめる
またこの2つとは独立に「理解力」も知的活動に不可欠だとしています
つまり、彼は「知能」に質的に異なる複数の側面があることを指摘しました。
Francis Galton(1822-1911)は知能をゼロイチよりも連続的なものとして捉えました。
しかし、それよりも世に最も影響を与えた彼の知能観は、以下のようなものでしょう。
「知能は生物学的な性質であり、遺伝もする」
そう、それはまさしく「優生学 eugenics」の産声でもありました。
ちなみに「GaltonがCharles Darwinの従兄弟でもある」と言えば、一層納得されるでしょうか。
この時代から優生学は進化論と心理学の鬼子であり続けてるわけですね。
そして「知能を客観化する試み」は19世紀に結実します。
Alfred Binet(1857-1911)が最初の学校用知能テストを開発。
※フランス人なのでBinetでビネ(ビネー)と読みます
これが現代の知能テストの原型になっていると言われています。

次の項では、これが近代という時代の必然でもあったことを提示しましょう。
社会の変化が「知能テスト」を求めた
社会の近代化と知能テストの成立は決して無縁でも偶然でもない、という話をしていきましょう。
次の3つの規模の社会を考えてみます。
- 生まれつき職や生き方が決まる社会
- 適度な分業制の小規模な村社会
- 産業が大規模で人が流動的な大規模社会
(多くの社会が1から3への変遷をたどっていることにはほぼ異論はないでしょう)
このそれぞれの社会で、人間を「適材適所に割り当てる」ことを考えましょう。
1. 生まれつき職や生き方が決まる社会
この場合、何も問題ありません(ありますが)
誰もが生まれた時の家や役割にしたがって、やるべきことをこなせば良いのです。
2. 適度な分業制の小規模な村社会
これは「村長」のような人がいる小コミュニティです。
構成員は隣人たちと融通しながら作業を分配できます。
「あいつは家を作るのが上手い」「あいつは稲刈りが速い」
といった評判が確立すれば、その村の中での相互評価に応じて分業もしやすいです。
3. 産業が大規模で人が流動的な大規模社会
ここからが問題です。
分業制のメリットを引き出すため、適した人を適した職場で働かせることは社会全体の生産効率に関わります。
しかし、少数の統治者が多くの民を束ねるような大規模社会では「どの人がどんな能力に長けているか」を全て管理者が把握するのは困難です。
代案の一つは縁故採用。もとい推薦制。
小さなコミュニティの中で「才能がある」と見なされた人たちを、小コミュニティの権力者(村長など)が独断と偏見で選出。
そして各地から推薦された候補者が学校や養成所で訓練を受けていくということですね。
古代エジプトや中世ヨーロッパが例に挙がりますが、江戸や明治の日本もインテリ層はこういう風に「個人的な縁故で先生に弟子入りする」方式は珍しくなかったようですね。
推薦よりも公平かつ体系的な選抜法を求めて生まれたのが、「テストで多数の候補者を一斉に序列化する」という方法です。
例えば英国では19世紀に軍の官僚をテスト選抜する方式を確立しています。
しかし人類史の中で最も早くこの方式に到達したのは古代中国でしょう。
筆記試験批判として「科挙のような旧態依然の~」という話はしばしば挙がりますが、むしろ西洋のテスト史から見ると、
「西洋文明が近代に至ってようやく到達した最先端の選抜法を千年以上も先取りしてる中国ヤバい」
なんですね。
近代西洋の話に戻しましょう。
19世紀以前の教育といえば現場での教育(on the job)が常識でした。
しかし19世紀後半のフランスを端緒に、普通教育が始まりました。
そこで初めて、「普通の子が出来る早さで勉強についていけない子」が可視化されたわけ。
民主主義革命を成し遂げた国フランスでは、この「出来ない子」をなるべく多くの人が納得するよう、客観的な形で選別する必要性が生じました。(区別した後にどういう対応をするかは別として)
その任務のために白羽の矢が立ったのが、先述のAlfred Binetでした。
Binetから始まった知能テスト
Binetは、「子どもの知能を測る」ことの出発点としてまず
1. 知能は年齢が上がるに従って単調増加する
この事実に着目しました。
彼は「知能を反映する」と考えられる様々なテストーー例えば「簡単な計算」「図形の模写」「口頭の指示に従う」などを用意しました。
そして、これらを実際の子どもに試した上で、「年齢の低い子は出来ないが、年齢が高くなると出来るようになってくる」問題を抽出しました。
つまり、これらの問題で「何歳の知能なら解ける問題か」を実験的に推定することにしたのです。
例として、具体的には「6歳児の75%が解ける問題」を「6歳用の問題」としています。
計算法は割愛しますが、「6歳用の問題が概ね解けて7歳用の問題がいくつか解ける」と「6歳○ヶ月」みたいな感じにスコアが出ます。
こうやって、「この子のテストの到達度は何歳に相当するか」を「精神年齢 Mental Age: MA」と定義したのです。
(ここで言う「精神」とは気質や人格などではなく、「頭脳のはたらき全般」を指していると考えると良いでしょう)
例えば、実年齢が7歳の子だったら、
精神年齢8歳なら「通常より少し賢い子」、
精神年齢6歳だったら「少し知能が低い子」、
として判断しよう、ということですね。
Binetは「学校に入ってから勉強で落ちこぼれる子は、入学時から知能が普通の子より低いはずだ」という想定の下でこのような検査を作りました。
(直接の語源かは分かりませんが「知恵”遅れ”」という言葉もこれと同様の発想が根底にありますね)
初めに言ったように、知能テストは元々「精神発達遅滞の児童を就学時に見つける」という目的で作られたわけです。
しかしBinet自身は「特別支援教育での活用」を主張したにも関わらず、結果的にこの検査パラダイムは「健常児の知能を数値化する」ことに転用されるようになりました。(参考図書2参照)
Binetの知能検査は、様々な改造や翻訳がなされて広まりました。
特にスタンフォード大学のLewis Terman教授がビネーの検査を英訳したものは、「スタンフォード-ビネー知能検査」として現在まで知られています。
日本でよく使われる「田中-ビネー式知能検査」も、最初の版はこの「スタンフォード-ビネー知能検査」を基にしています。
Binetは「精神年齢」という指標を考案しましたが、「知能指数」という指標を確立したのはTermanです。
「知能指数」、すなわち「IQ (intelligence quotient)」ですね。
Termanは「年齢の相場に対して、この子の知能は高いのか低いのか」を分かりやすくしようと考えました。
そこで「精神年齢」を「実年齢」で割って、
IQ=100×精神年齢÷実年齢
という式でIQを定義してみたわけです。
実はIQを定めるのに今はこの定義式は使われていないのですが、「IQ」という概念だけは引き続き使われています。
Binetの検査が普及するのと並行して、これと独立に様々な「知能を測る」検査も考案されました。
そして、その集大成が1930年代にWechslerの考案した知能検査です。
これは当時の検査の中でも優れて統計的に裏付けられていました。
彼の生み出した「WAIS」「WISC」は、現在に至るまで改訂が重ねられ、今はそれぞれ第4版が出てます。
WechslerはIQを統計的に再定義し、「精神年齢」という指標を用いない定義式を作りました。
この話まで混ぜると少し説明が煩雑になるので、稿を改めて解説記事を書こうと思います。
今回はここまで。
★ひとことまとめ
3. Wechslerが大成させた知能検査とIQの定義が現在に引き継がれている
参考文献
書籍
1. Earl Hunt: Human Intelligence(2010, Cambridge University Press)
2. 村上 宣寛: IQってホントは何なんだ? (2007, 日経BP)
☆もっと知りたい人向け
村上 宣寛:
IQってホントは何なんだ?
2007, 日経BP
本稿をまとめるにあたって、『Human Intelligence』に次いで参照しました。
前半ではほぼ知能検査の歴史が語られており、Hunt氏の著書よりも詳しいです。
この研究会について
以下の書籍の輪読会をインターネット上にて定期開催しています。
Earl Hunt: Human Intelligence(2010, Cambridge University Press)
本記事は輪読会の内容を元に、メンバーのトークも盛り込んでサマライズしたものです。
トピックや話の流れは上記のテキストを踏襲していますが、内容は再解釈の上で大幅に加筆や再編を加えています。
なお、研究会に参加をご希望の方はこちらの記事もご覧ください。
この記事を書いた人
狐太郎
最新記事 by 狐太郎 (全て見る)
- AIサービスを活用した英文メール高速作成術 - 2023年3月28日
- 大学生・院生に便利なAIウェブサービスまとめ【2023年2月版】 - 2023年2月22日
- 「読書強者」が「速読」に価値を見出さない理由【隙間リサーチ】 - 2022年9月23日