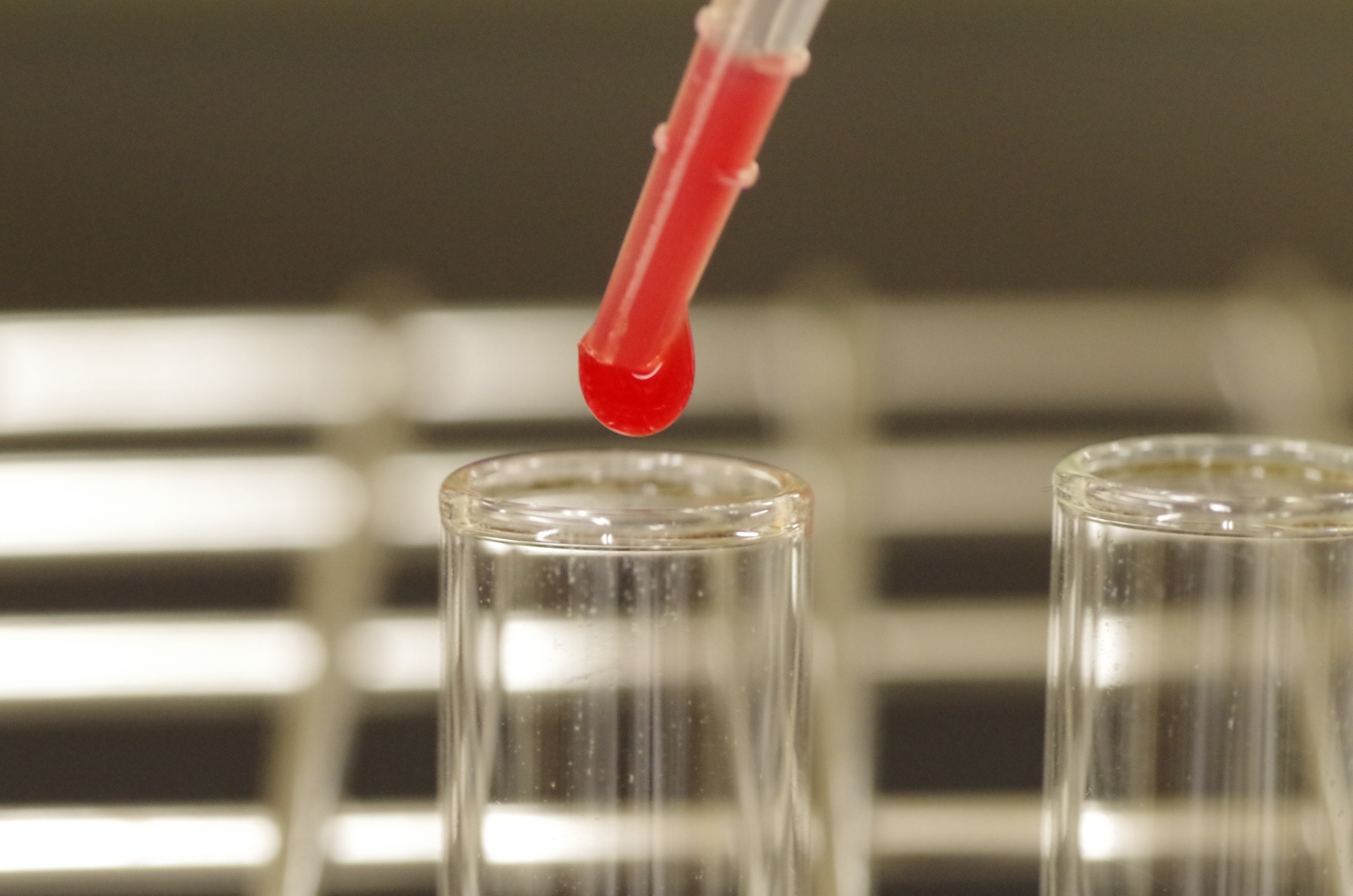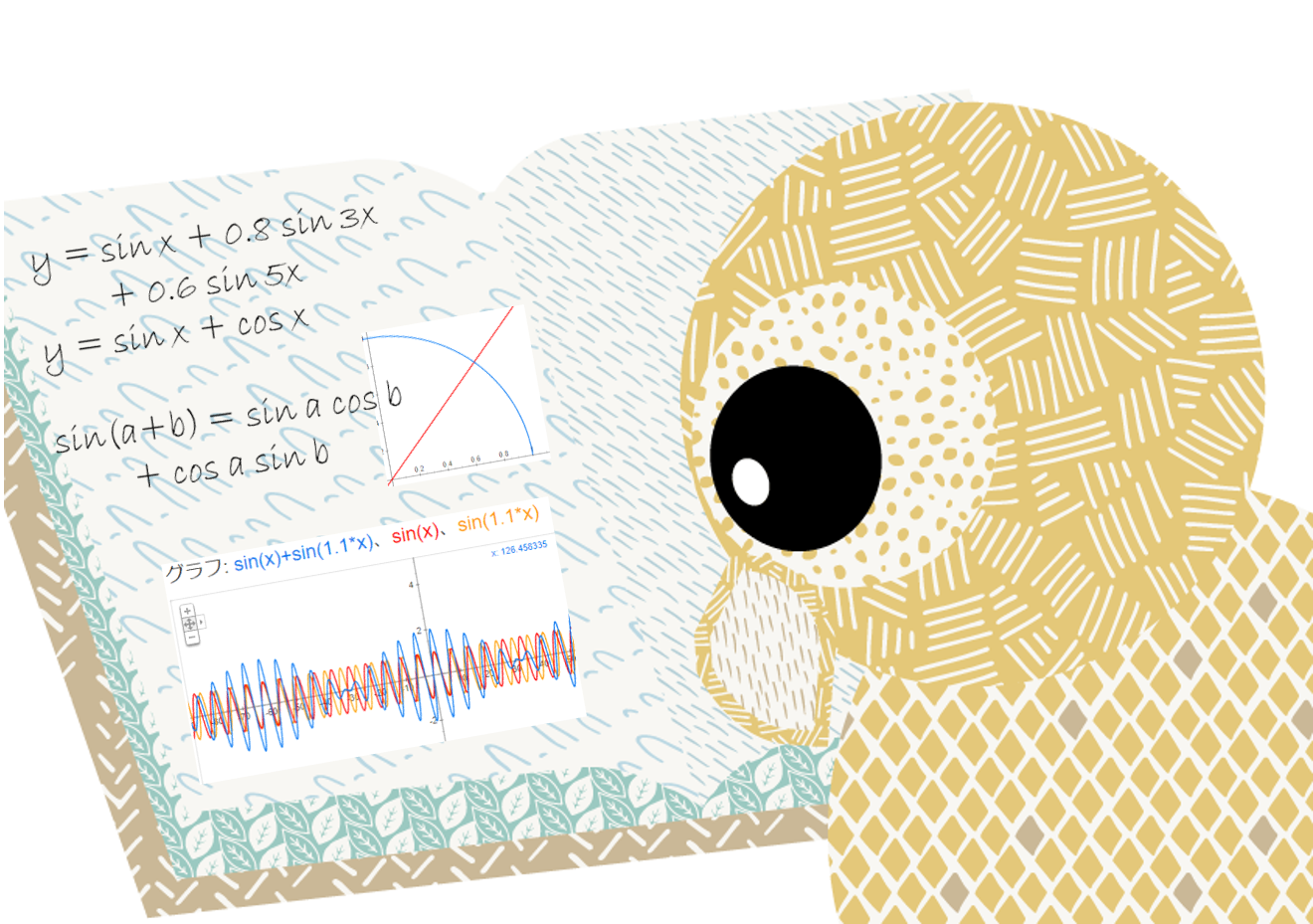今回は少し毛色が変わって、テクノロジーの話です。
「脳の研究でこんなことが分かった」というニュース記事を読む時、「どうやって調べたか」は意識されにくいかもしれません。
しかし、脳の研究には何種類かのアプローチがあり、手法の性質により結果も制約を受けます。
つまり、脳研究の内容を適切に読み解くためには、手法に関する知識は不可欠なのです。
そんなわけで、今回は「脳の研究手法」を紹介していきましょう。

脳研究の黎明期
CTもMRIも無い時代には、「脳」は「直接目で見る」ことでしか確認出来ませんでした。
つまり、死んだ人の頭蓋骨を開けて、中身を見るということです。
近代的な脳研究の黎明を告げたのは、
Pierre Paul Broca(1824-1880)による「ブローカ野Broca’s area」の発見です。
Brocaは臨床の外科医でしたが、たまたま足の感染症で治療を受けに来た患者が「『タン』としか話せない」という奇妙な症状を持っていることに興味を持ちました。
この患者は残念ながら数日後にこの感染症で亡くなったわけですが、Brocaは直ちにこの患者を解剖して、「脳の左前頭葉の一部が壊れていた」ことを突き止めました。
そして、偶然にも同じ年にもう一人、「脳卒中で話すことが出来なくなった患者」に出会いました。
この患者は翌年、たまたま別の病気で死んだのですが、Brocaはこの患者も解剖しました。
そして結果は予想通り。
この患者は脳卒中で「左前頭葉の同じ部分」が壊れていたのです。
画像はWikimedia commonsから
このようにBrocaは「患者の生前の認知機能」を調べ、「死後の脳の状態」と対応させました。
彼が発見した「発語に関連する左前頭葉の部位」は「ブローカ野」と呼ばれることになりました。
ブローカ野の発見から13年後の1874年、同様の手法でCarl Wernickeが「ウェルニッケ野Wernicke’s area」と呼ばれる別の言語領域を発見しました。
こうした研究の蓄積で、19世紀には「心的な機能は脳に由来する」という考え方が確立されました。
前頭葉損傷を負った「Phineas P. Gage」や、両側海馬切除を受けた「H.M.」の知見も、これに連なるものと言えましょう。
「脳の損傷と認知機能との対応」を調べる学問分野は「神経心理学neuropsychology」と呼ばれ、脳研究の黎明期から現在に至るまで続いています。
脳の「構造」を可視化する
時代が下り、人類は物理学を使って様々なものを可視化するようになってきました。
ここから紹介するのは、そんな発明品の数々です。
CT
画像はWikimedia commonsより
「CT」という言葉を聞いたことがない人はいないと思いますが、正式名称はご存知でしょうか?
略さずに言うと、「computed(computerized) tomography」という名前です。
つまり「コンピュータで計算して作った断面図」のこと。
物理的な原理は健康診断でも撮るような「レントゲン」と同じなのですが、レントゲンを色々な方向から撮影することで三次元の情報を復元することが出来るわけです。
X線の発見とコンピュータの発展によって、初めて人類は「頭蓋骨の中に入ったままの状態の脳」を可視化出来るようになりました。
世界で最初に作られた「X線CT装置」が脳の検査のために使われたことは、「脳を視る」ことがいかに人類の悲願であったかを示唆する話だと思います。
この検査は「X線(レントゲン)を使って検出した情報をコンピュータで解析して断面図にしている」ので、名付けるとしたら「X線CT」という呼び方が正しいはずなのですが、今では慣用的に「CT」と言ったら「X線CT」を指す習わしになっています。
後述するPETなども「コンピュータの演算によって作る断面図」ではありますが、普通そちらを「CT」とは呼びません。
MRI
画像はWikimedia commonsより
CTが開発された1970年代のほぼ同時期に、MRI(核磁気共鳴画像magnetic resonance imaging)も発明されました。
これは簡単に言えば、「外から強い磁場を掛けた時の水素粒子の挙動を検出する」ことで頭蓋骨の中の三次元情報を再構成しているのですが……正確な原理はめちゃめちゃ難しいので、ちょっと踏み込んだ説明は勘弁して下さい。
詳しく興味がある方はこういう総説とかもどうぞ
小川邦康(2019)『MRI(磁気共鳴画像法)』(リンクはPDFファイルです)
このMRIの開発史では、実は日本人が多大な貢献をしています。(このあたりを参照)
日本は世界的に見ても異常なほど人口あたりのMRIが多いのですが、それは医療の公費負担が大きいこと以外にもそういう歴史的経緯があるからかもしれません。
また、CTでは(リスクはごくわずかとはいえ)放射線に晒されるのに対し、MRIの磁力は原則として人体に悪影響を与えないとされています。このため、現在は脳研究ではCTよりMRIの方が好まれる傾向にあります。
また、MRIは「どのように磁場をかけるか」「どんな信号を検出するか」という2つのパラメータを変えることで、「同じ脳を違う見方で見る」ことが出来ます。
拡散テンソル画像(diffusion tensor imaging: DTI)はその一例です。
DTIでは、「水粒子(中の水素原子)がどの方向にどのくらい動きやすいか」を検出します。
例えば、そこにある水分子が「左右や上下の振動に比べて上下に動きやすい」場合、そこには「上下方向に線維がたくさん存在している」可能性が考えられます。
同様にして、「どの方向に線維が向かっているか」を場所ごとに推定して繋げ合わせます。
脳の中で「線維」といえば、神経回路でのケーブルに当たる「白質white matter」ですね。
通常のMRIが「脳の地形図」だとしたら、DTIは交通網を可視化した「脳の路線図」だと言えます。
画像はWikimedia commonsより
このような技術の発展もあって、近年では脳を「パーツの複合体」ではなく「ネットワーク」として捉える考え方も主流になってきました。
脳の「機能」を可視化する
CTとMRIによって、「構造」が分かるようになりました。
しかし、多くの研究者が本当に知りたいのは「機能」の方です。
「〇〇を考えている時、脳のどこを使っているんだろう」という疑問に答えるために、「機能画像」の技術が生まれました。
PET
画像はWikimedia commonsより
「PET」の正式名称は「陽電子放出断層撮影 positron emission tomography」と言いますが……今では一般的にも「PET」という呼び名が一番定着していますね。
PETは簡単に言えば「放射性物質を体内に入れて、放射線を外から検出する」という検査です。
CTは「外から光を当てて、その『影』を見る」という検査でしたが、
PETは「体内に『光源』を入れて、その『光』を見る」というわけです。
放射性物質は無数に種類があるので目的によって使い分けますが、脳の検査のために使われるのは放射性を持たせた「FDG」という物質です。
これ、簡単に言うと「グルコース(ブドウ糖)のニセモノ」です。
よく働く神経細胞はグルコースを活発に消費します。
ですから、この「ニセモノのグルコース」が吸収されているところほど、神経がよく働いているということになるのです。
ただ、脳活動による糖代謝の変化は健常者ではそれほど極端に変化しないので、例えば「文章を読んでいる時に活発になる脳部位」というような検出には向きません。
てんかんや脳腫瘍や認知症など、病気によって脳の一部のグルコース消費が極端に変化しているような場合にはPETで検出することができます。
余談ですが、この「FDG PET」検査は「がん検診」でも使われます。
理由は同じで、「がん細胞は普通の細胞よりグルコースをたくさん吸収する」からです。
fMRI
画像はWikimedia commonsより
今や機能画像検査の代名詞にもなっています。
fMRIの「f」は「機能function」です。
脳の神経細胞は、活発に働くほど酸素をたくさん消費します。
酸素を多く消費する神経細胞がいるところには、酸素を多く届けるために血流が多くなります。
このため、脳の局所では「神経細胞があまり働いていない時」と「神経細胞が活発に働いている時」とで、血流が異なります。
fMRIでは、「酸素を持っている血(oxy-Hb)」と「酸素を渡した後の血(deoxy-Hb)」の磁性が異なることを利用して、これらのバランスの変化を信号として検出できます(BOLD信号)。
このように、「神経活動の増加」を「脳血流の増加」として間接的に検出するのがfMRIです。
例えば、「A.モノクロ写真を見た時」と「B.カラー写真を見た時」で比べた時、BOLD値の変化があった脳部位には「『色』によって活動性の変化する神経細胞がある」と推定できるわけです。
以前、fMRIの研究を見て「自閉症の病態は脳の血流不足である」と論じている方がいましたが、これは上記理論の理解不足による誤解だと思われます。
fMRIにおいては「BOLD値の変化は神経細胞の活動性の変化を間接的に見ている」という論理なので、その根本的現象は「特定の刺激に反応する神経細胞の応答性が低い」と解釈すべきです。
そもそも、ある活動を「した時」と「しなかった時」の差分を見るのがfMRIなので、デフォルトの状態において「脳が血流不足であるかどうか」はfMRIで判断できるものではありません。
fMRIは「脳内の活動変化」を捉える数少ない方法なので、爆発的に応用が増えました。
しかし、「血流の変化を見る」という性質上、どうしても「神経活動そのもの」とは数秒単位のタイムラグがあります。
このため視覚などの研究には盛んに使われてきましたが、音声言語ようにリアルタイム性の必要な認知機能の研究にはやや不向きでした。
脳波
上記の2つに比べると、「脳波」は非常に素朴な動作原理です。
Luigi Galvani(1737)が発見したように、神経は電気によって活動しています。
ならば電気の情報を取り出して調べよう、というのが脳波の発想です。
脳波の物理的な原理は「電位の差分を記録する」ことで、実は「心電図」と全く同じ原理です。
英語では心電図が「electrocardiogram」(electro:電気+cardio:心臓+gram:図)なのに対し、
脳波は「electroencephalogram」(electro:電気+encephalo:頭+gram:図)なので、
実は「脳電図」と訳す方が忠実なくらいです。
脳波には無秩序なノイズや発振も信号として混ざっているため、当初は脳波から複雑な認知機能を検出するのは難しいと思われましたが、「事象関連電位event-related potential:ERP」が登場して状況が変わりました。
「人の顔を見た時の脳波」には、「人の顔と関係した脳波」と「無関係な脳波」が混じっています。
そこで、「人の顔を見た時の脳波」を何十回分も平均するのです。
すると、統計的な現象として、「無関係な脳波」はランダムなため平均するほどゼロに近づきます。
一方、「人の顔と関係した脳波」は一貫して同様に出現するので、平均しても相殺されず残ります。
このように、「何かを提示した時に起きる電気活動」を脳波の平均によって検出したものを「事象関連電位」と言います。
脳波はミリ秒単位で脳の挙動を観測できるため、一瞬の現象を捉えるような実験に非常に強いです。
一方、20個かせいぜい100個程度の電極で脳をカバーするので、「位置」の情報に関してはfMRIより劣ります。
「PET」「fMRI」「脳波」はそれぞれ、「グルコースを使って活動する」「酸素を使って活動する」「電気を出して活動する」という神経細胞の異なる面を利用して「脳の活動」を検出していることになりますね。
以上、今回の記事では脳のメジャーな研究手法について概観しました。
こうして見ると、X線、γ線、そして磁気に電気……と、物理学・工学の先端研究によって脳研究が発展してきたことがよく分かりますね。
脳を知るためには物理の勉強も不可欠……ということで。今回はここまで。
おわりに
★ひとことまとめ
★参考文献
・書籍
Hunt, E. (2010). Human Intelligence. Cambridge University Press
山鳥重:言葉と脳と心 失語症とは何か.講談社現代新書, 2011/1/18
髙橋雅士(監),前田正幸(編):新 頭部画像の勘ドコロ.メディカルビュー社,2014/3/24
・Web
Wikipedia:『コンピュータ断層撮影』、『核磁気共鳴画像法』 、『fMRI』
山鳥重:
言葉と脳と心 失語症とは何か.
講談社現代新書, 2011/1/18
著者は日本における神経心理学の大家です。
BrocaとWernickeの研究論文について、一般書でこれほど詳しく解説している本は無いと思います。
黎明期の脳研究者は、「脳と心」という問題について、何を見て何を考えたのか。
本書には非常に興味深い視点が詰まっています。
小泉英明:
脳の科学史 フロイトから脳地図、MRIへ.
角川SSC新書, 2011/3/10
脳研究に使われる検査装置について異常に詳しく書いてある一般書。
著者はfMRIの開発にも携わった経歴を持つ、ガチガチの工学畑の方です。
本記事で紹介したような装置の原理や開発過程について興味のある方にはオススメです。
★この研究会について
以下の書籍の輪読会をインターネット上にて定期開催しています。
Earl Hunt: Human Intelligence(2010, Cambridge University Press)
本記事は輪読会の内容を元に、メンバーのトークも盛り込んでサマライズしたものです。
トピックや話の流れは上記のテキストを踏襲していますが、内容は再解釈の上で大幅に加筆や再編を加えています。
なお、研究会に参加をご希望の方はこちらの記事をご覧ください。
この記事を書いた人
狐太郎
最新記事 by 狐太郎 (全て見る)
- AIサービスを活用した英文メール高速作成術 - 2023年3月28日
- 大学生・院生に便利なAIウェブサービスまとめ【2023年2月版】 - 2023年2月22日
- 「読書強者」が「速読」に価値を見出さない理由【隙間リサーチ】 - 2022年9月23日