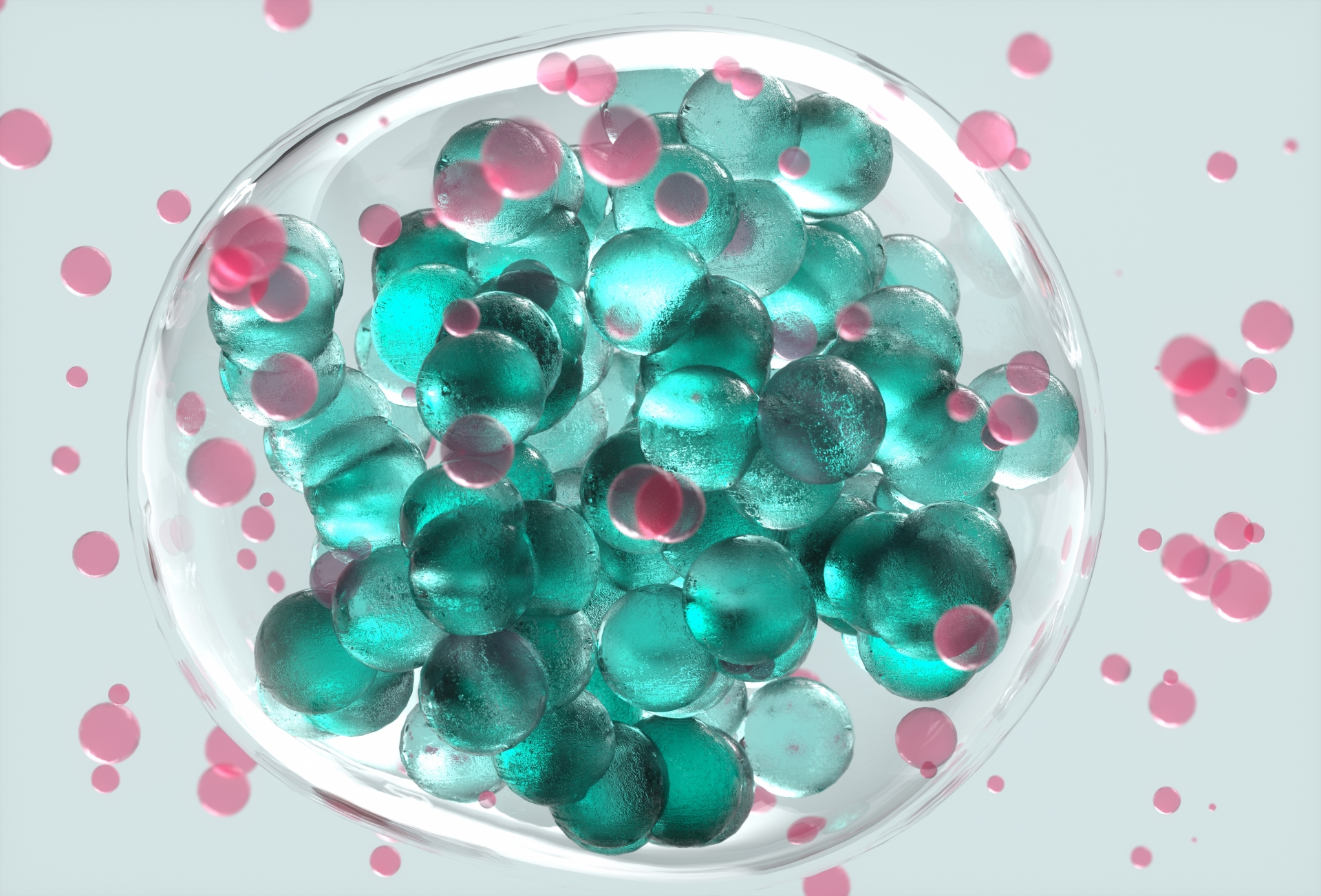〈生命〉とは何だろうか
表現する生物学、思考する芸術
談社現代新書, 2013/2/15
目次
第1章 つくりながら理解する生物学―細胞をつくるとは?
第2章 「細胞を創る」研究会をつくる
第3章 合成生物学の源流をめぐって
第4章 表現する生命科学―生命美学という試み
第5章 現代芸術における生命
「生命の仕組み」がここまで物質的に解明されてきたのなら、そろそろ「人工的な生命」が作れるのではないだろうか
――分子生物学の本を読んでいると、そんな期待が湧き上がってきます。
そして、実際にそんな「夢」に取り組んでいる人々が本書の主役です。
近代的な生物学では、「細胞」を「生物」の最小単位としています。
ヒトのように大型の生物は基本的に「多細胞生物(=一個体が複数の細胞の複合体として構成されている)」ですが、細菌や酵母やマイコプラズマは「細胞1個だけの生物」です。
このような例を見ると、細胞1個でも立派に「生物」と言えるわけですね。
そして細胞は「細胞膜」という袋に包まれており、袋の中には「生命の設計図」とも呼ばれる「DNA」が入っています。
では、有機物質で袋を作り、その中にDNAを注入したら「生物」と言えるでしょうか?
結論から言えば、このような実験的合成物は「生物とは言えない」というのが、一般的な「生物」の定義に基づいた見方でしょう。
有機物の袋の中にただ乱雑にDNA混じりの塩水を混ぜただけでは、そこから「転写」も「翻訳」も起こらないはずで、結果として生物の最も重要な要素である「自己複製」には到底至りようが無いからです。
では、どうやったら「DNAからタンパク質が生み出されるまでの流れ」を再現できるでしょうか?
では、どうやったら「自己複製する有機物の袋状構造」が生み出せるでしょうか?
そして、それが可能となった時に、「『人工的な生命』を生み出せた」と言えるでしょうか?
本書のテーマの一つは「『人工的な生命』をどのように作るか」でありますが、上記の議論を見れば分かるように、「何をもって『人工的な生命』と呼ぶべきか」という境界線の議論が本書のもう一つの柱となります。
(さらに言えば、これは「どこからが『生命』か?」という問題と「どこからが『人工』か?」という2つの問題が複合しています)
この問題を扱うために著者は、文理(そしてアート)の壁を超えて知見を交差させていくことの重要性を繰り返し強調しています。
「実際のモノ」を扱っている生物学者の多くは、従来こうした思想的な議論に踏み込むのを避けがちでした。
法学や人文学といった専門家の多くは「現代の生物学にはどこまでのことが出来るのか」をあまり具体的に把握してきませんでした。
このような状況をもどかしく思う著者にとって、第2章や第5章は本書のコンセプトから外すことは出来ないテーマだったのだろうと思います。
読み手にとってこれらは「学術的な知識」として蓄積されるような内容ではありませんが、本書の中にそれなりの紙面を割いて位置付けられていた理由は何となく伝わってきます。
話を戻しつつの余談ですが、本書で私が個人的に興味を惹かれたのは「トラウベの人工細胞(Traube cell)」という科学実験です。
これは19世紀の科学者のアイディアで、当然ながら「生物の細胞を人工的に合成する」ものではありません。
ぶっちゃけ簡単に言えば「比較的シンプルな化学反応の連鎖」でしかないのですが、その成長の様子を眺めていると何とも言えない「生命らしさ」を感じます。(上の動画をどうぞ)
これをもう少し複雑で手が込んだものにしたならば、あるいはこの動画を全く化学的知識の無い状態で先入観無しに見たならば、私たちはこれを「生命ではない」と見なせるでしょうか。
筆者は「生命であること」を定義するにあたって、私たちの直観に根付いた判断を重視していますが、私はむしろ「直観によって導く『生命』の線引き」の不確かさを味わったような気分になりました。
ともすれば、生物学者が「社会における生命観」へと手を広げないことは、ある種の「良識」とみなすこともできるのではないでしょうか。
学術的に「生命」を追求する場面では、定義の堅牢さを優先させるべきであって、そこに「通俗的な意味での生命」が相互乗り入れすると船が山に登ることになるのでは……という危惧が払拭できません。
良くも悪くも扇動的な本だと言えるでしょう。
学問で人間の世界観を塗り替えようと思っている人であれば、本書から何らかの刺激が得られるのではないかと思います。
★NEXT STEP
細胞の中の分子生物学
ブルーバックス
2016/5/20
「生物の専門家でない人が分子生物学を学んで『生命と物質の境界』について考えるには何がいいだろうなー」というコンセプトで探してみましたが、案外普通に王道のところに落ち着きました。
『〈生命〉とは何だろうか』は「生命の仕組みをどうやって模倣するか」がテーマでしたが、基本となる「生命の仕組み」についてはあまり体系的に詳述されてないんですよね。
「生体細胞の基本的な動作原理」と「それを支える物質的基盤」については本書のような本で体系的に一度学んでおくと理解が深まって良いかなと思いました。
理系総合のための生命科学 第5版
分子・細胞・個体から知る“生命”のしくみ
羊土社, 2020/2/23
さらにガチで行くならこれ。
高校生物非履修の理系学生が大学レベルの入り口までキャッチアップするためのテキストです。
簡単に言えば内容は高校生物のマクロ生物学の範囲を削ってミクロ生物学の内容を2倍くらい詳しくした感じになってます。
一般書としてはほぼ最高レベルで、これより上だともう専門書になってきますね。
狐太郎
最新記事 by 狐太郎 (全て見る)
- AIサービスを活用した英文メール高速作成術 - 2023年3月28日
- 大学生・院生に便利なAIウェブサービスまとめ【2023年2月版】 - 2023年2月22日
- 「読書強者」が「速読」に価値を見出さない理由【隙間リサーチ】 - 2022年9月23日