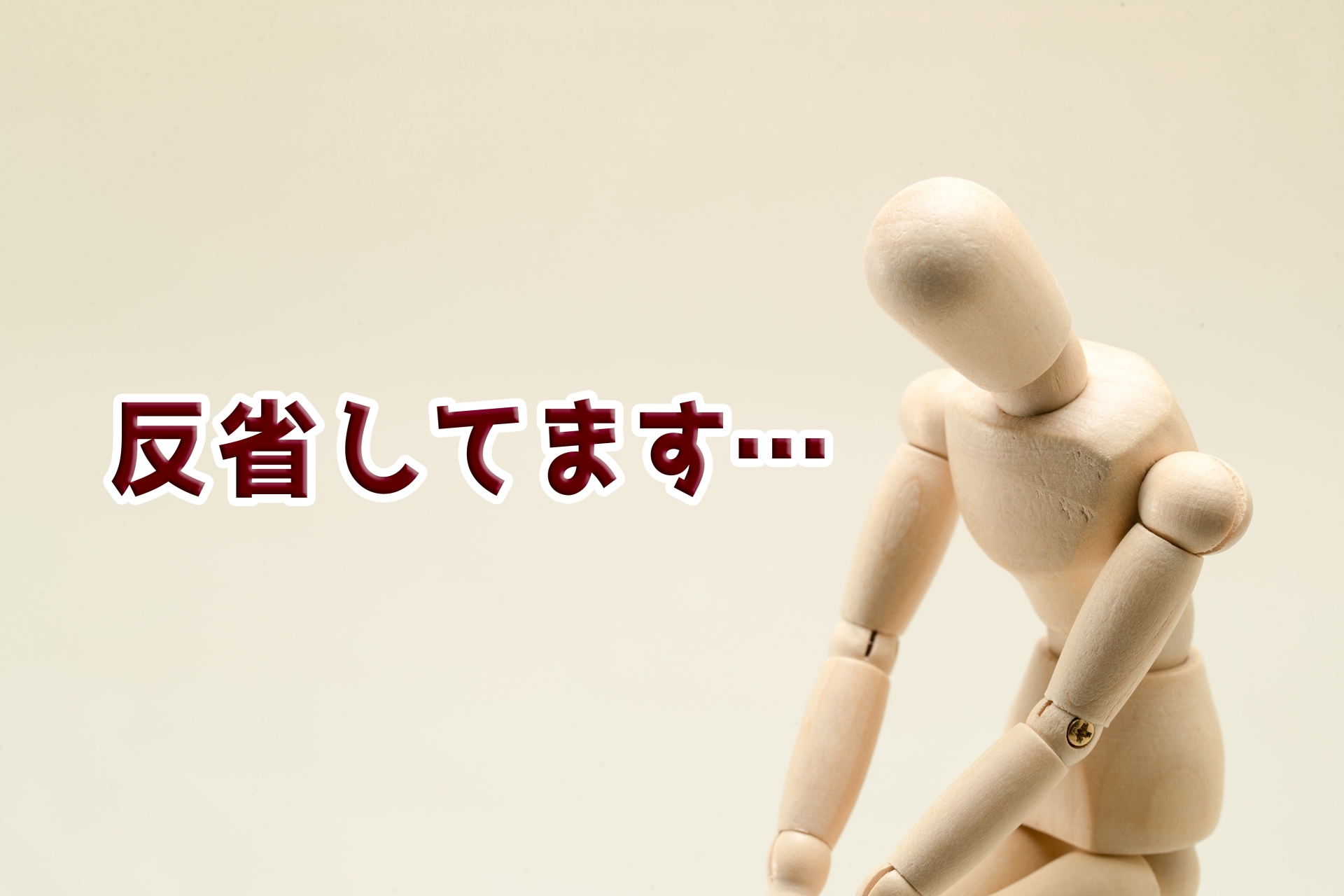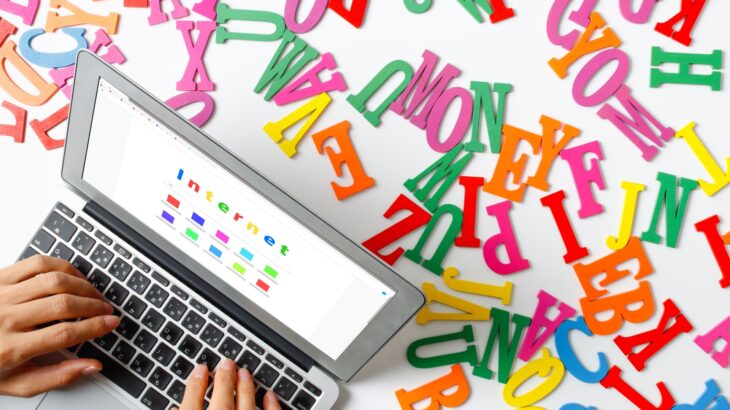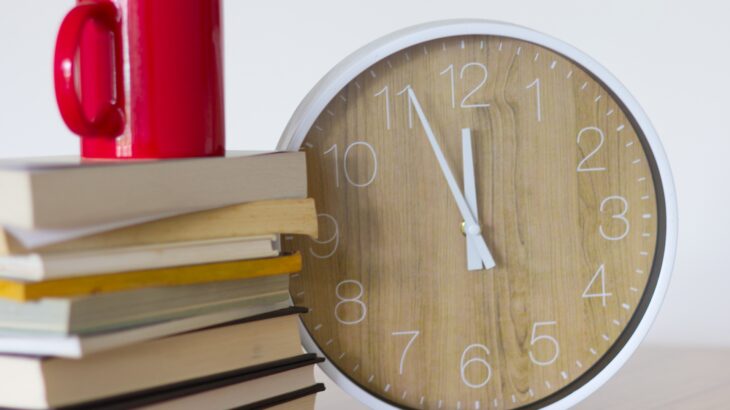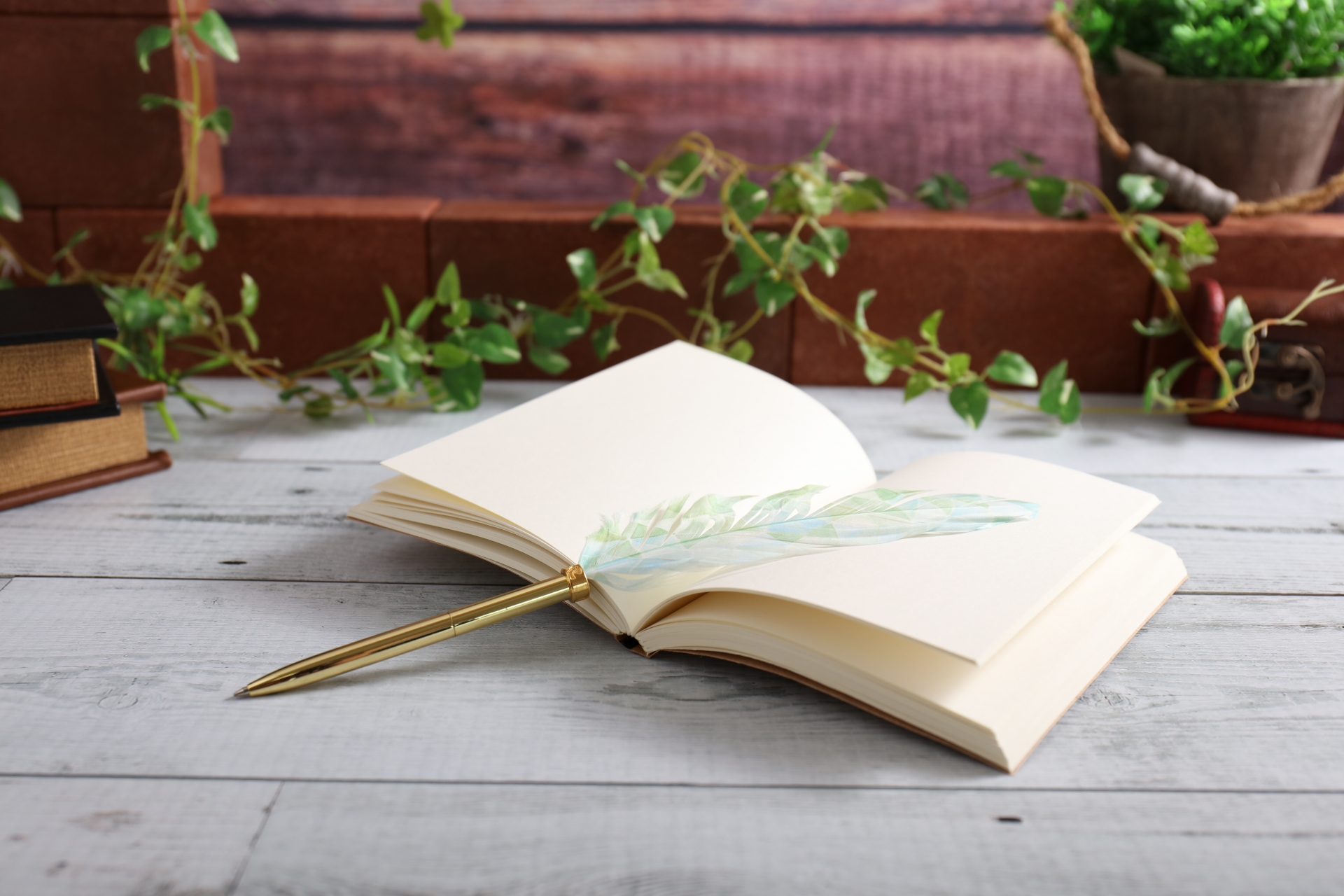反省させると犯罪者になります
2013/5/17, 新潮新書
今回は攻めたタイトルのこの本です。
著者は長年に渡って刑務所における受刑者の教育に携わっており、本書もそこでの経験から書かれています。
このタイトルを目にした時に、反射的に「『反省』の何が悪いのか」と言いたくなる方も多いかもしれません。しかし、本書の主張は「『反省』が悪い」ということではありません。
本書の主張は、「強制力で『反省させる』ことに教育的効果が無い」ということです。
「悪いことをした人が自分の内面や過去の行いと向き合い、その結果として『反省』が自然と湧き上がってくる」ことについては肯定的に描かれています。
「『反省』を目的化して強制する」ことの悪影響が本書の本題なわけですね。
また、これと連動して、「『反省したかどうか』を目安にした量刑や教育を行うべきではない」ということについても述べています。
こうしたスタンスには「反省のフリが上手くなる」以外の効果は無い、と。
これは言われてみるともっともなことで、第三者が「反省したかどうか」を確認する方法が無い以上、犯罪者にとって「本当に心から反省の言葉を述べること」と「上手な反省の真似をすること」は報酬としては等価であり、より手軽かつ確実に実行できるのは明らかに後者です。
むしろ「本当に自分の頭で考えて、心からの言葉を述べる」ことが常に「立派な反省の文章」に繋がるわけではないのですから、「求められているのは『上手な反省の真似』だ」と解釈されても仕方ありませんね。
要求する側の意図がどうであれ、現実としてそういうインセンティブ構造になってしまっているわけです。
そして、そのことが内面的な更生の機会を奪ってしまっている、というのが筆者の主張です。
筆者は受刑者の声を拾い上げ、「模範的な反省」が実際の反省を全く伴っていないことや、一見「反省させる」のとは逆に見えるアプローチで更生に繋がった例を提示しています。
「受刑者が『反省の言葉』を綴らされる時にその水面下には何があるか」という点についても、なかなか類を見ないほど丁寧に綴られ、分析がなされております。
これ自体は非常に有用な情報ですし、筆者の論にも一定の説得力があります。
しかし、表題の「反省させると犯罪者になる」については、本書の中には具体的な根拠がなく、これは飛躍だと言わざるを得ません。
実際に「反省させる教育」と「犯罪率」を結びつけるデータは本書の中に登場しないのです。
一般書は多少センセーショナルなタイトルを付けないと手に取られにくい、という事情はあるかと思いますが、飛躍した結論をタイトルにするのはやや行きすぎかなと感じます。
賢明なる読者は、本書を引いて「反省させると犯罪者になるんだぞ!」と主張することの無きよう、お気をつけください。
内容自体は面白かったです。
★NEXT STEP
入門 犯罪心理学
ちくま新書, 2015/3/4
「各論的な本」の後には「総論的な本」の紹介。
犯罪と関連する心理的傾向を分析したり、それを犯罪の捜査や抑止に役立てる心理学の分野を「犯罪心理学」と言います。
本書はタイトルの通り、予備知識無しでも読める犯罪心理学の入門書です。
特に『反省させると犯罪者になります』ではあまり言及されなかった「エビデンスに基づいた犯罪対策」の視点が強調されていますので、併せて読むと相補的な視点が得られるかと思います。
狐太郎
最新記事 by 狐太郎 (全て見る)
- AIサービスを活用した英文メール高速作成術 - 2023年3月28日
- 大学生・院生に便利なAIウェブサービスまとめ【2023年2月版】 - 2023年2月22日
- 「読書強者」が「速読」に価値を見出さない理由【隙間リサーチ】 - 2022年9月23日